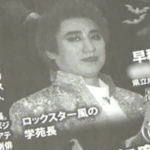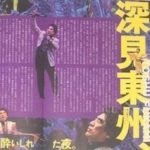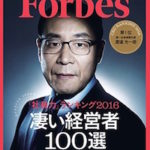前回は、ワールドメイト会員の間でも関心が高い、ブラインドゴルフの大会のことを紹介したけど、今日はそれとも関係するパラリンピックのことについて書いてみる。
今日から、パラリンピックがリオテジャネイロで始まった。
ネットにいろいろなことが紹介されているけど、その中でとても驚いたことがあった
パラリンピック陸上種目の走り幅跳びでは、オリンピック選手の記録を上回る記録を出した選手が出場するそうだ。
スポーツ競技として、パラリンピックがハイレベルになったとは聞いていたけど、オリンピック選手よりもすごい記録を出す選手がいるなんて、想像してみたこともなかった。
ところが、そんな大記録を出したがゆえに、義足がジャンプに有利になっているのではないかという疑いをかけられて、今回のリオ・オリンピックに出場を希望したけども、最後は断念したそうだ。
それで少し調べてみると、義足も軽量でアスリートのために高性能になっているのは確かだそうだ。そして激しく競技するので、足に負担がかからないように、わずかな微調整などを繰り返し、その人の足にフィットするものを製作するそうだ。
従って非常に高価なものになってしまう。そのために先進諸国や、個人的にゆとりのある選手しか使用できないため、用具的に不公平になるのではないかという課題も障害者スポーツにはあるそうだ。
その意見は、わからないでもないけど、この走り幅跳びの選手が健常者と一緒に行うオリンピックに出場できないのは、また別な問題なのかもしれない。
自分もそう思ったから人のことは言えないけど、パラリンピアンが、オリンピック選手より優れた記録を出すことはありえない、という偏見から来た可能性も言われている。
もしそんな気持ちから出たことであれば、少しおかしい気がする。
仮に記録が低ければ、特に問題視されなかった可能性が高いと言われているだけに、疑問とされる基準が、オリンピック選手の記録を抜くことだとすれば悲しい気がする。
いくら義足が進化したからと言っても、電動ロポットではないわけで、自分の足のようにはいかないだろうからね。義足で歩けるようになることだけでも、大変な努力と勇気がいるそうだから。
ましてや義足で走ったり飛んだりすることは、大変な努力というだけではすまないだろうし、また、非常な危険を伴うのではないかと思う。
義足をつけることは、普通の人が竹駒に乗ってるようなものだとか。
そして、義足で競技に挑戦することは、縫った傷口が開いてしまうことがあるので、普通は勧めないらしい。
それでも競技をやりたいという情熱で、多くのパラリンピアンが生まれているんだろうから、すごいことだなと思う。
(世界が感動したプレゼン、佐藤真海さんの東京五輪・復興への想い )
ところでパラリンピアンに関心を持ったのは、2013年9月に行われた国際オリンピック委員会総会で、2020年の開催都市を決める最終プレゼンテーションのトップを務めた佐藤真海さんを知った時だった。
笑顔満点の、とても感じが良い人で、しかも流暢な英語で堂々と、ものすごく感動的なプレゼンを行った人なので、覚えている人も多いと思う。
その中で、はじめて障害を持つ人だということを知った。
すごく心揺さぶるものがあったし、上の動画を見ると、どんな人かも少しわかると思う。
このときのスピーチの中で、北京でパラリンピックに出場してスポーツの力を知ったと言われていた。
宮城出身であり、3.11の津波では実家が被災し、その体験を踏まえて、津波で被災した時に皆で一緒に頑張ったことと、スポーツの精神は同じだと思ったそうだ。
それがスポーツの力であるし、希望を与え笑みを与え、人々を結びつけるのがスポーツだと思うと話されていた。
2016年のオリンピック招致では、いまひとつ招致に際して何を訴えていくのかよくわからなかったけども、この2020年の時は、佐藤さんのスピーチにあるように、スポーツの力の素晴らしさを訴え、オリンピックの持つ価値が日本で新たに開いていくという印象を強く持った。
その2か月前には東京おいて、深見東州先生が会長を務める国際スポーツ振興協会と、同じく総裁を務める世界開発協力機構が主催したスポーツ平和サミット東京大会が、大々的に開催されていた。
その時は深見先生の友人であるイベンダ・ホリフィールド、ミシェル・クワンなど世界的なアスリートも集まった。
また、世界のスポーツ界の専門家による会議が行われ、スポーツの力が、いかに世の中に貢献しているのか、社会を素晴らしい方へ変えることができるのかを、いろいろな角度からの話で聞くことができた。
スポーツの力は無限大であり、平和や復興に貢献できることを印象ずけられた。それからスポーツの力というものを、すごく意識するようになったのを覚えている。
そして現在は、世界の国際会議では「開発と平和のためのスポーツ」が注目されていて、日本政府はスポーツを通じた国際貢献事業として「Sport for Tomorrow」を世界的に公約し、日々実践しているそうだ。
10月には、世界経済フォーラムの協力と、官民の連携で「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」(主催:文部科学省、スポーツ庁、文化庁)というイベントが開催される。
スポーツ・文化芸術の発展による新たな産業の創出、スポーツ・日本古来の文化(道)の魅力、成長戦略と連動した日本ブランドなどを海外に積極的に発信することを目指しているそうだ。また、それによって対日直接投資の拡大につながる期待があるそうだ。
その会議のリーダである文部科学省参与の藤沢久美氏の話によると、今世界では、ユネスコ主催の「MINEPS」(体育・スポーツ担当大臣等国際会議)をはじめ、国際的な場でのスポーツの議論がとても増えているそうだ。
それでスポーツの力というものを、今回の「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」期間中のスポーツ大臣会合でも、日本から発信するそうだ。
ということで、スポーツの力というものが、本当に大きくクローズアップされてきている。
東京オリンピック・パラリンピックへと向かう中で、大きな日本のテーマになっているようにさえ感じる。
また、「開発と平和のためのスポーツ」という言葉はどこかで聞いたことがあるなと思っていたら、スポーツ平和サミットが2014年はニューヨークで、2015年は南アフリカで開催されたけど、その名称がWorld Sports Values Summit for Peace and Developmentだった。
深見東州先生の、スポーツの力で社会をよりよくという活動が、日本や世界でも主流な考えになっていくのかもしれない。
そして、そうなるように、影響を与えているんじゃないかなと思った。


リオパラリンピック 寛容・共生、いま輝く 12日間の熱戦開幕
南米初開催となる障害者スポーツの祭典、第15回夏季パラリンピック・リオデジャネイロ大会が7日夜(日本時間8日午前)、マラカナン競技場で開幕した。国際パラリンピック委員会(IPC)によると、直前に2カ国が出場を辞退したため、159カ国・地域から約4400人が参加。132人の選手団を派遣した日本はポルトガル語のアルファベット順で82番目に旗手の上地(かみじ)結衣(ゆい)(エイベックス)を先頭に笑顔で入場行進した。
競技は8日から本格的に始まり、18日まで12日間、トライアスロンとカヌーの2競技を新たに加えた22競技528種目で熱戦が展開される。五輪同様、今大会でも初めて難民チームが結成され、シリアとイラン出身の2選手が出場する。大会のスローガンは五輪と同じ「A New World」(新しい世界)で、開会式は「他者への寛容、尊重」をテーマに、多民族国家・ブラジルから共生社会の重要性を発信した。
#リオ2016 南米初の #パラリンピック !12日間の熱戦が幕を開けました。
リオの興奮はまだまだ続きます。すべてのパラリンピアンに声援を! #RiotoTokyo #rio2016 pic.twitter.com/jBX5yQDsca— Tokyo 2020 (@Tokyo2020jp) 2016年9月8日