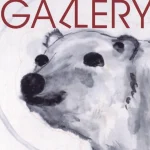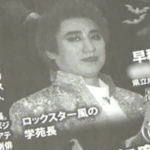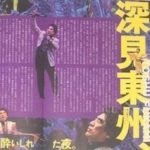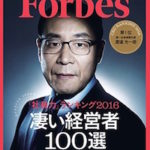前回は第25回目の深見東州バースデー個展の感想をつらつら書いたけど、「ビジネス分析と経営評論」というテーマで、社会人や経営者へのアドバイス的な講演も開催されていた。
その中で、最新の情報について書かれた本とか、業界誌を読むことの重要性についてお話しされていたけど。そういえば、最近は本をあまり読んでなかったなーと、ちょっと反省した。
たしか、本を読まなくなったら成長も止まるみたいな話を、以前、ワールドメイトでされていた気がする。
忙しくて読まなくなったり、面倒くさくなって読まなくなったり、つい、どうでもいいことに時間取られて読めなくなったりするよね。もっと読まないといけないけど。

そして文芸論の講演も行われた。「俳句・短歌・詩・川柳・小説評論」というテーマで、文学について2時間半ほど語られた。
何度も言われているのが、「詩心(ポエム)を理解することが、文化レベルの高い教養の始まり」ということだった。
「人間の持つ最も高貴なものが詩心であることを理解できる、咀嚼できるのが教養の始まりである」
論語の「詩に興り、礼に立ち、楽に成る」の、詩に興りというのはそういう意味になるそうだ。
そして礼節を尽くす、礼節をわきまえている人が教養がある人であり、さらに音楽のようにみんなと一緒に楽しむというのが、楽に成るという意味になるそうだ。
楽というのは音楽と、楽しむという二つの意味があり、自分の役割を果たしながら、みんなで音楽を作るという調和や協調性があり、喜びを共有でき、楽しめるような人でないと、教養がある人とは言えないと孔子は言いたかったそうだ。

長編と短編の違いの話も面白かった。短編は短いから、どんなに荒唐無稽な話であっても大丈夫らしい。
でも長編になると、リアリティがしっかりなければ、読む人は納得しないし怒りだすと言われていた。
そんな説明を阿刀田高さんから聞いたそうで、深見東州先生は自分は短編に向いていると思われたらしい。
深見東州先生は短編集を3冊出されているけどね。どれもかなり荒唐無稽な物語になるよね。
でも、その独特の世界が、よく意味がわからなくても、なんだか面白い。文体も個性があるけど読みやすいし、読後感は爽やかな感じになるし。
長編小説のようなリアリティは無いけど、意味がわからないから、つまらないとか思ったことがないからね。

そして文学について、フランスは文体における表現の美意識が文学と言われていた。
イギリスはイマジネーョンが文学だそうだ。たとえばハリーポッターのようなイマジネーションをかき立てられるような作品が文学なんだろうね。
日本における文学は、物語と歌なんだよと、折口信夫の最後の弟子と言われる岡野弘彦先生から聞かれたそうだ。
國學院の教授であり、深見東州先生が短歌などを学んできた先生だよね。
物語としての面白さがあり、長く人々に愛されて残ってきたものに高い文学性がある、と深見東州先生は言われている。
日本の漫画は素晴らしいものが多いけど、高尚な文学作品に比べて低く見られているのはおかしいと、以前言われていたと思うけど。
同様に、ショートショートや、SF作品とかも、文学界では純文学よりも下に見られているらしい。
深見東州先生は、物語に、ジャンルによる芸術性の高い低いは無いと考えられている。
日本の漫画家って、ホントに魅力的な作品を描く人が多いからね。面白い作品を書く小説家もたくさんいるとは思うけど。
100年後は、もしかするとアニメ作品が文学作品として、高い評価を受けることだってあり得なくは無いよね。

古典の日本文学には、伊勢物語とか源氏物語とか、物語としての面白さもだけど、歌も必ず入っている。
だから、物語と歌の歴史を知らないと、日本の文学はわかりませんよと、岡野先生は言われていたらしい。
歌には、日本には和歌と呼ばれる古典詩、多くは短歌になるけど、昔からあるよね。
今なら俳句や川柳も含まれるけど、それらの定型詩は、半分は言葉の調べであり、半分は詩的な言葉の意味になるそうだ。
言葉が詩的であり、意味がわかれば良いのではなく、言葉の調べが良くないといけないそうだ。
川柳は洒脱な面白さも必要になるけどね。
深見東州先生によると、そんな定型詩における芸術性とは、「その人らしいもので、その人にしか詠めないもので、意外性があり、在り方のパターンにハマらないもの、類想にハマらないもの」と言われていた。

最終的に文学とは、良いところも悪いところも全て含めて人の心を理解できて、人の心を動かせるものと言われていた。
そういえば、深見東州先生は人間の酸いも甘いも噛み分けてある。どちらの面も理解し愛した上で判断したりお話をされている。
文学がある人は、言葉や文章で、それを表現できるそうだ。
だから文学がない政治家は、人を動かせないから1流の政治家にはなれないし、文学性がない宗教家は宗教家とは言えないと言われていた。
神様も、文学性がある祈りだと動きやすいと、ワールドメイトでは聞いたことがあるし。
今回の文学の講演を聞いて、深見東州先生がチャールズ国王をはじめ、海外の優秀な政治家や、VIPな人たちと仲良く、親しい関係が築けるのは、このような高い文学性と教養があるから、それも大きいというのがよく理解できた。